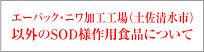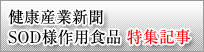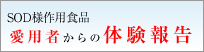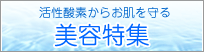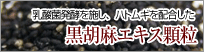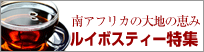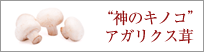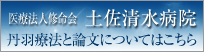- トップページ >>
- 丹羽療法に使用されている“天然素材”:チャーガ
チャーガ(カバノアナタケ)
白樺のがん
チャーガは、和名をカバノアナタケ・シベリア霊芝・岳樺などと呼ばれ、「サルノコシカケ類」あるいは「多孔菌類」という木材腐敗菌の一種です。白樺の木に寄生し、白樺の栄養分をたっぷり吸収しながら長い年月をかけてゆっくりと成長し、最後にエキスを吸い尽くし枯らしてしまうほど生命力が旺盛です。チャーガがエキスを吸い白樺の木を枯らしていく様子は、体内でがん細胞が増殖し健康な細胞を破壊していく過程によく似ています。
ロシアの文豪でノーベル賞作家のアレキサンドル・I・ソルジェニツィンの小説「がん病棟」は、がん病棟の現場を事実に基づいて描いており、 1968年当時のソビエト連邦国内で、あらゆる雑誌から掲載を拒否されるなど、社会的問題を投げかけました。その本中で、チャーガは、「白樺のがん」「白樺の幹に生じる黒い醜い塊」「白樺の病気」「白樺の腫瘍」などと表現され世界的に知られるようになりました。この奇妙な名前は、チャーガが白樺の木に寄生することに由来しています。

元々白樺の木は寒冷地に自生するたくましい樹木で、ロシアでは昔から樹液を体に良い天然ジュースとして愛飲してきました。この樹液には、各種の多糖類、サポニン、アミノ酸、有機酸、ミネラルなど、体に必要な有効成分が豊富に含まれていますので、その薬効は多岐にわたります。この白樺の樹液を吸い取って成長するチャーガは栄養の宝庫であることは想像がつきます。さらにキノコ本来の有効成分も含有されていますので、チャーガは白樺の有効成分とキノコの有効成分の相乗効果が期待できるといわれています。
ロシアでは、チャーガの薬効は古くから知られており、数世紀にわたりチャーガを煎じてお茶代わりにしたり、薬酒にして飲用したという歴史があります。しかも、日常的にチャーガを飲む習慣があった村では、がん患者が極めて少ないという記録も残っています。
チャーガは、シベリア・ロシア連邦・中部ヨーロッパ・中国・日本の北部といった寒冷地に広く分布し、-20℃にも耐えて生育しますが、これを見つけるのが非常に困難で、カバノキ科の木にしかできないうえ、生長が非常に遅く、寄生してから10~15年かけてようやく直径50センチ、厚さ10~15 センチの大きさに達するからです。さらに大変なことは、山奥まで入ったとしても、他のキノコとの判別が難しく、一日中探し回っても見つかるか見つからないほど貴重なキノコゆえに、その稀少価値は「幻のキノコ」「森のダイヤモンド」とも呼ばれています。
民間治療薬として伝承された「チャーガ」の史実
世界中いたる所で長寿の村や健康に恵まれた地域などをマスコミがしきりに紹介していますが、理由を探ってみますと、必ずそこに住む人々の生活習慣の中に、伝統的に受け継がれているものが必ずといっていいほど存在します。
たとえば、アマゾンの源流域、ペルー、ボリビアあたりに高度な文明を築いた古代インカ帝国の子孫といわれるインディオたちは、タブベイヤ・アベラネダエという巨木を「神の恵みの木」として崇めてきました。そして、この樹の内側の樹皮を剥いで煎じ、万能に効く薬として使ってきました。
インカ帝国の歴史に疫病流行の記録がないのもそのお陰だと言われています。現代においても民間薬として伝えられているタブベイヤ・アベラネダエは多くの人に飲用されています。
同じロシアのコーカサス地方は、世界的に有名な長寿の地域ですが、ここでは古代から山岳民族に受け継がれるケフィアと呼ばれる菌を牛乳に加え発酵させて作る発酵乳があります。最近の研究では、免疫調整機能の向上、ストレスに対する抵抗力増強などが解明されています。
その発酵乳がコーカサス地方の人々の健康を永年に渡り支えてきたと言われています。
チャーガの薬効も昔から経験的にしられるようになり、ロシアでは煎じてお茶代わりにして飲む習慣があります。また、ヨーロッパでも16~17世紀ころから民族薬として利用されてきました。
世界的にチャーガが知られるきっかけになったソルジェニツィンの「がん病棟」(1968年)は忠実に基づいて描かれており、モデルになった医師も存在するといわれています。興味深いことに小説に登場するがん患者らが、一様に自然治癒力に関心を示している点で、その利用法や入手法などを話し合う箇所があります。
がんに蝕まれた患者達が病棟での治療に限界を感じ、他に治療法を模索していたところチャーガの存在を知り、患者たちは強い関心を示します。「その方法は医学的に認められているか」「そんなに効くなら医者はなぜ治療に使用しないのか」「医者は自分の薬を広めたいばかりにこの治療法に反対する人もいるだろう」「我々患者に選択の余地はないしね」など、がん治療を取り除く環境は40年近く経過した現在でも当時と一向に変わっていないようです。
チャーガの抗がん効果を医学的に証明
チャーガの研究は1859年にフェレーベン医師の論文で「チャーガががんに有効である」と発表されたのをきっかけにスタートしました。その後、1862年フルヒト、1896年スミルノーフが「チャーガで各所のがん治療に成功した」と研究報告をしています。
そして、1951年、旧ソ連邦科学アカデミーカマロフ記念植物研究所とパブロフ記念第一レニングラード医学研究所による共同研究が本格的にスタートしました。この研究ではチャーガの抽出物を用いて臨床試験が行われ、特に胃や腸など消化器系のがんに顕著な効果が認められました。それから1972年カローヴィンがこれらの臨床データを基に喉頭がんの臨床試験を行いました。いずれも症状の重い第四期の喉頭がん患者27名に対し、これまでの治療と水
200gに対し40gのチャーガの噴霧剤を併用して行い、毎日5~6分の吸入時間で10日間続けました。結果は5回目の吸入でほとんどの患者の症状が改善されました。
第一レニングラード医学研究所のフェドートフ教授は医師として長くシベリアに在住中、チャーガを飲用する村人たちにがん患者が極めて少ないという事実に関心を持っていました。そこでフェドートフ教授を中心とした研究チームは1973年から10年間にわたり、重度の胃潰瘍の患者150人にチャーガを処方する実験をしました。胃潰瘍は20~25%の確率でがん化するといわれています。これは、胃潰瘍を患った約4人に1人ががんになる可能性があるということです。
つまり、潰瘍の段階でがん化の抑制力を試す実験です。結果は驚くべきもので、チャーガを処方した重症胃潰瘍患者150人の内、がん化が認められた患者は10 年間で1人も存在しませんでした。この理由について教授は、「がん化の原因となる胃潰瘍そのものを抑制できた」「チャーガが本来持つがんの抑制作用により相乗効果がもたらされた」と報告しています。さらに、1996年パシンスキーは、人工的にがんを発生させたマウスを使用し、チャーガ製剤と乾燥チャーガ抽出物の反応の違いを実験しました。
その結果、いずれのマウスも死亡が確認されず、両方ともがんの形成を抑制する効果があることがわかりました。しかし、著しい効果が得られたのは、乾燥チャーガ抽出物で、チャーガ製剤の3倍の有効率を示しました。
日本国内においても、1996年、静岡大学の水野卓名誉教授の研究グループにより、本格的に研究がスタートしました。水野教授は「チャーガ多糖の抗腫瘍活性と血糖降下作用」という学術論文で、「チャーガの水溶性多糖及び水不溶性多糖の両方に抗腫瘍作用とともに正常マウスの血糖値を降下させる作用が認められた」と発表しています。その本体が、β‐グルカン、ヘテログリカン、及びそれらのタンパク複合体だと科学的に証明しました。
- ロシアでのチャーガ研究の歩み
-
- 1859年フェレーベン「チャーガの治療作用についての報告」
- 1862年フルヒト「身体各所のがん治療成功例」
- 1896年スミルノーフ「チャーガによるがんの治療例」
- 1970年スハーノフ「人工的に起こした腹膜炎、結膜炎、眼瞼炎の進展に対する6%チャーガ煎剤の影響」
- 1972年カローヴィン「咽頭腫瘍に対するチャーガアエロゾール(噴霧剤)の効果」、ドスイチョーフ/ブイストローヴァ「チャーガ製剤の乾癬と慢性胃腸管・肝臓疾病の併発患者への影響」
- 1993年グリベーリ「胃腸管の運動排出機能に対する、乾燥チャーガ抽出物の影響とその鎮痛効果についての研究」
- 1995年ガバネンコ「チャーガを基にしたバルサム(芳香油、鎮痛剤)ベリョースカに関する研究」
- 1996年Yu・I・グニネンコ「カザフスタン北部および中部におけるカバノアナタケの資源量の問題について」 パシンスキー「公認チャーガ製剤と乾燥チャーガ抽出物、その分別物の胃への保護効果についての研究」 ブルチク「子宮頸管の腫瘍細胞に対する2種類のチャーガ抽出物の細胞毒素作用の研究」
- 1997年ルイジョーヴァ「超音波抽出法で得られた乾燥チャーガ抽出物の薬理学的特長の研究」
- 1998年ルズモフスカ「子宮頸管の腫瘍細胞における未乾燥チャーガ抽出物の効果」 B・G・パシンスキーと研究チーム「カバノアナタケ乾燥エキスの抗腫瘍、順応性促進、抗腫瘍作用」
- 2000年ベラルーシ国立科学アカデミー微生物の研究所研究グループ「カバノアナタケのメラニン・コンプレックス」
- 2001年アイナベコーヴァ「チャーガ浸剤の抗オキシダント効果の実験と臨床研究」